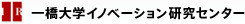Claims about Benefits of Open Access to Society (Beyond Academia)
ElSabry, ElHassan, Chan, Leslie: Fernando Loizides(編)『Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices: Proceedings of the 21st International Conference on Electronic Publishing』
IOS Press(2017/06/30)